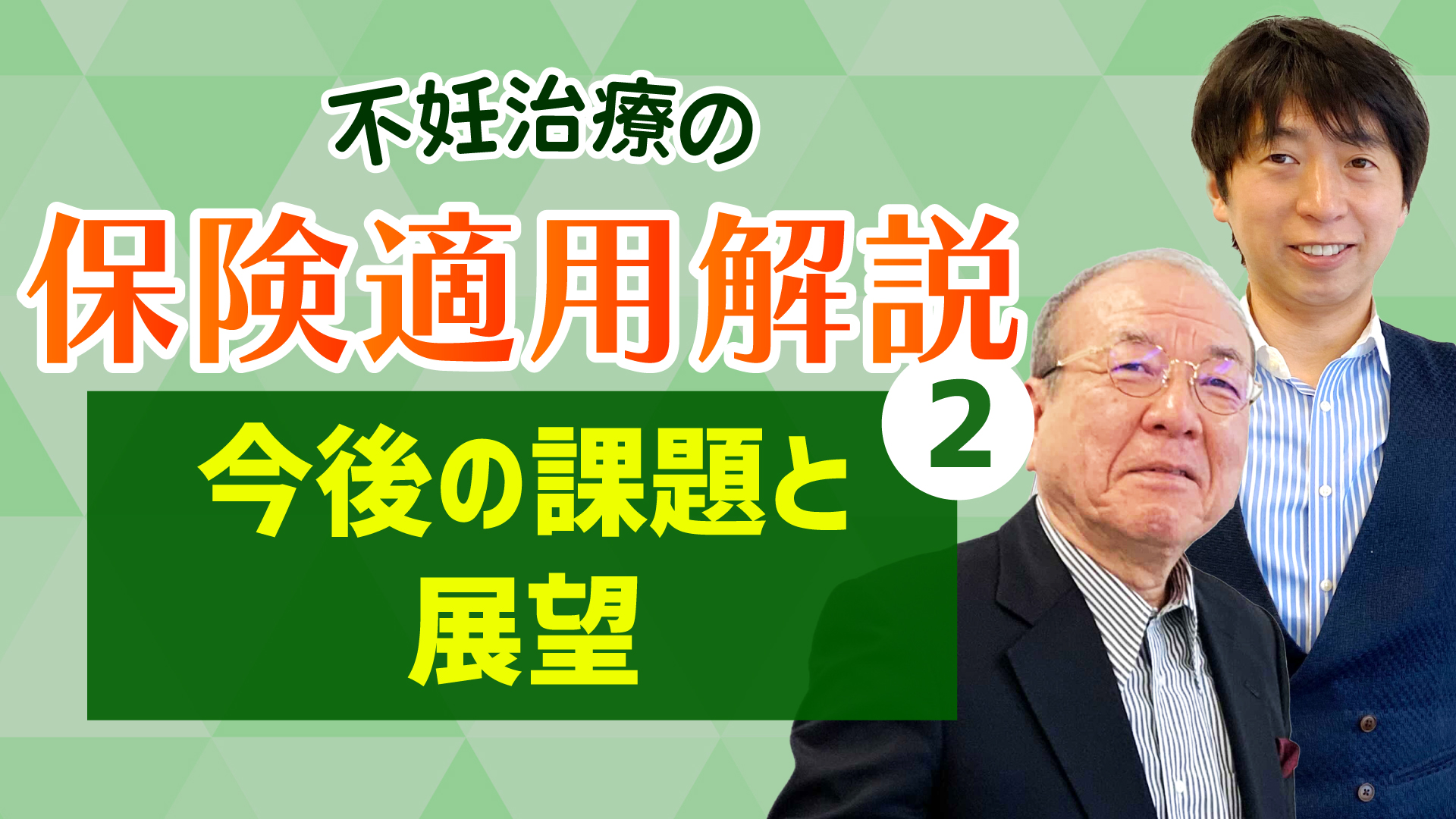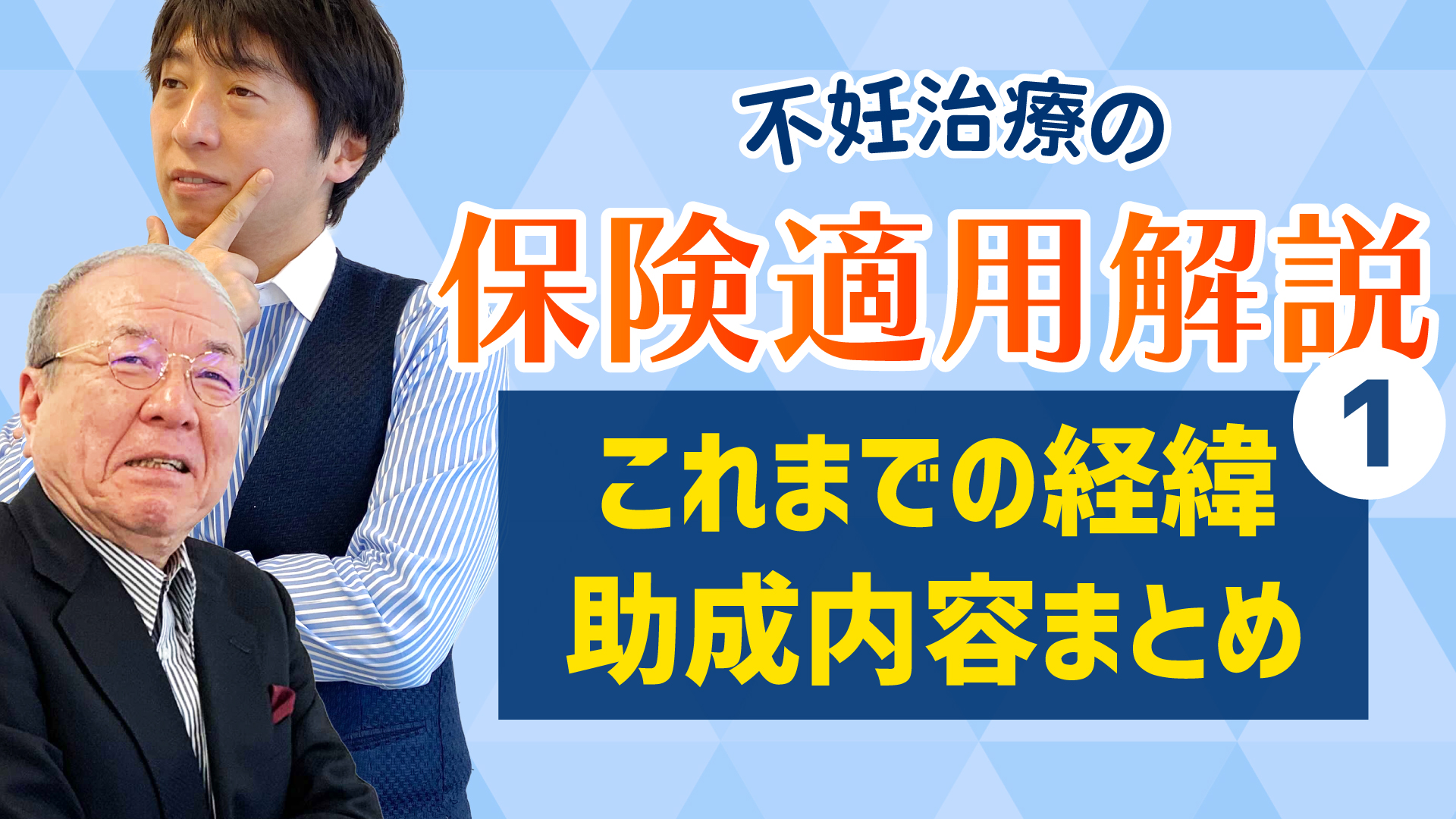2022年04月13日
不妊治療が保険適用に。助成金や保険内容を解説
不妊治療が保険適用に。助成金や保険内容を解説
不妊治療の保険適用は、待ち望んでいた方も多いはず。金銭的負担が少なくなれば、クリニックに通うハードルも下がるでしょう。不妊治療の保険適用の内容や助成金について詳しく解説いたします。
不妊治療の保険適用とは
不妊治療はお金がかかると認識している方も多いでしょう。2022年の4月から不妊治療に必要な治療の大部分は保険診療が適用されることになりました。
これまで、不妊治療は自費診療であり、助成金はあるものの、大部分を自分たちで負担しなければなりませんでした。助成金は申請しても振り込みまで数か月かかることを考慮しなければなりません。そのため、20代など若くして不妊に悩んでいる方や、結婚して間もない夫婦は、まず資金を用意してからと考えるケースも少なくありませんでした。
金額負担は10割から3割に
保険が適用になる治療内容や投薬については、金額の負担が今までの10割から3割になります。一回の通院で、会計が10万、20万になることも珍しくない不妊治療において、この差額は大きなものです。
例えば金額で治療回数を決めていた夫婦が、100万円の自己資金で今まで1回しか治療を受けられなかったところ、保険適用になったら、3回治療を受けてもおつりが来ることになります。実際は自己負担が必要な治療もあるため、こんなに単純な計算にはなりませんが、妊娠のチャンスが増えることは間違いないでしょう。
治療内容ごとの保険適用の違い
保険が適用されることにはなりましたが、自己診療が継続される治療もあります。通うクリニックによって対応が違ってくるため一概には言えませんが、保険適用になる治療、ならない治療について、一例をご紹介します。
保険適用になる治療内容
一般不妊治療のタイミング法や人工授精、高度不妊治療の採卵・採精、体外受精・顕微授精、胚培養、胚凍結、受精卵の移植、基本的な治療は全て保険適用の対象となります。担当医と相談しながら、保険が適用される内容だけで治療を完結することは可能だと言えるでしょう。
保険適用にならない治療内容
では、どのような内容が保険適用の対象外になるかというと、クリニックによっても変わってきますが、検査やオプション的な内容は自費診療が継続されている場合があります。
例えば、治療に入る前にクリニックが独自で設けている検査や、妊娠率を上げるための処置や投薬などが挙げられます。また、同じ日の治療内容に自費診療のものがあると、その日の会計が全て自費になるケースもあるので、事前に確認が必要です。
具体的な費用について
都内のクリニックを例に、自費診療と保険適用の料金を比較してみましょう。
採卵して、受精卵の新鮮杯という状態の卵を得るまでの合計金額は
【自費診療】
刺激周期で407,000円
自然周期で297,000円
採卵を行う際の麻酔や、採卵後の培養、凍結などは別に費用がかかります。
(例)7 個採卵し媒精で受精、胚盤胞培養で凍結 2 個の場合、約430,000円と挙げられています。
【保険診療】
採卵基本料金9,600円(0個)
2個~5個採卵できた時は合計20,400円
(例)刺激周期(採卵 10 個、新鮮胚移植、余剰胚凍結 2 個の場合)約 170,000円
それぞれ移植には別途費用が発生しますが、こちらのクリニックでは、自費診療は多くのものが組み込まれている料金設定ですが、保険適用は料金が個別に設定されているイメージです。簡単に比較するのが難しいように思えますが、例を見ただけでも料金が随分と抑えられていることがわかります。ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった時、高額療養費制度を使えます。
年齢や回数など、保険適用の条件
保険適用には条件がありますが、これまでの助成金と同じ内容です。
年齢制限は治療開始時、女性の年齢が43歳未満であることです。回数の制限は、1人目の治療開始時に助成の年齢が40歳未満の場合6回、43歳未満の場合3回であり、それぞれ1子ごとなので、2人目を希望する場合には回数がリセットされます。
すでに不妊治療をされている方の対応
令和三年度までに治療を始めている場合は、助成金申請の対象になります。また、移行期間として助成金を申請するか、保険適用の治療を勧めるか選択できる場合もあります。詳しくは医療機関に確認していただく必要がありますが、助成金・保険適用のいずれかは対象となりますので、年齢や回数の制限を超えていない限りは、全て自費で賄わなければならないということはないので、ご安心ください。
まとめ
不妊治療の保険適用についてご紹介しました。すでに治療を始めている方は、保険適用を選択すると以前受けられた治療が受けられないというケースも発生するかもしれません。保険適用を選択すると治療を受けられないのか、それともその部分だけ自費診療で同じように治療を受けることができるのか、受診している医療機関で確認することが大切です。
保険診療を上手に活用して、納得できる治療を受けましょう。
厚生労働省「不妊治療の保険適用」
https://www.mhlw.go.jp/content/000913267.pdf
杉山産婦人科「費用について」
https://www.sugiyama.or.jp/reproduction/cost